後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために始まった75歳以上の方が対象の独立した医療保険制度です。高齢化が進み、それに合わせて高齢者の医療費は増え続けています。高齢者世代も保険料と医療費の一部を負担し、みんなが安心して医療を受けられるしくみ(国民皆保険)を守り続けていくため、この医療制度が創設されました。
後期高齢者医療制度
75歳(一定の障がいのあるときは65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。制度の運営は、岩手県では岩手県内すべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合(http://iwate-kouiki.jp/)」が行い、市町村と役割を分担して運営しています。
| 広域連合 | 市町村 |
| 運営主体(保険者)となり・保険料の決定・医療を受けたときの給付・資格確認書の交付決定などを行います。 |
保険料の徴収・申請や届け出の受付・資格確認書の引渡しなどの窓口業務を行います。 |
対象となる人
- 75歳以上の人全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
- 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあると広域連合から認定された人(申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。)
一定の障がいとは
・国民年金法等障がい年金 1・2級
・身体障がい者手帳 1級から3級及び4級の一部
・精神障がい者保健福祉手帳 1・2級
・療育手帳 (A)
保険証[資格確認書]
被保険者証からマイナ保険証・資格確認書に変わります
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」)の交付が終了しましたが、現在お持ちの被保険者証は有効期限まで使用できます。
次に該当する場合「後期高齢者医療資格確認書」(水色)(以下「資格確認書」)が一人1枚交付されます。マイナ保険証をお持ちでなくても、医療機関等を受診される際に資格確認書を提示することで従来通り保険診療を受けることができます。
・新規で資格を取得した場合
・12月2日以降に、お持ちの被保険者証に修正があった場合
なお、当面の間、新たに資格を取得された方でマイナ保険証をお持ちの場合にも資格確認書をお送りします。
保険料について
保険料は全員が納めます(健保組合などの被扶養者だった人も保険料を納めます)
毎年7月に、(1)保険料額決定通知書(保険料の額を記載しています。)(2)納入通知書(保険料の納め方について記載しています。)を被保険者の方へ送付します。通知書が届いたら、保険料の額に加え、納め方が「年金天引き」なのか「納付書(口座振替)」なのかを確認してください。
|
保険料の納付方法は、「年金天引き」と「口座振替」のどちらかを選べます。年金天引きの場合は、手続きは必要ありません。口座振替での納付を希望される方は、手続きが必要です。(納付する保険料の年額は変わりません) (注意)
(備考) (1)口座振替にした場合、税申告の社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。(例えば、息子さんの口座から振替した場合は、息子さんの社会保険料控除に適用されます。) (2)年金天引きを希望されても、条件により天引きに変更できない場合があります。 |
保険料の決まり方
|
保険料=均等割額(40,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率7.36%) (備考)
|
軽減措置
(1)被用者保険被扶養者の方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった人は、2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。ただし、国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。
(2)均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者)所得に応じて、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。以下の表をご覧ください。
| 軽減内容 | 世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の総所得金額等 |
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)以下 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+28.5万円×被保険者数以下 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+52万円×被保険者数以下 |
※年金・給与所得者数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
- 給与収入が55万円を超える(専従者給与は除く)
- 令和5年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
- 令和5年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
また、65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
|
事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。 災害を受けた場合など納付が難しいときは、分割納付や一定期間の徴収猶予を行うこともできますので、納期限までに納めることのできないときは、相談してください。 相談窓口は、税務課です。 |
病気やケガをしたとき(療養の給付)
病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、医療費の1割(現役並み所得者は3割)の一部負担金を支払うだけで、医療が受けられます。
(参考)課税所得が145万円以上であっても、次の条件に当てはまる方は、申請により、自己負担割合が1割になります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同世帯の被保険者で「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方。
(2)同世帯の被保険者が1人で、収入が383万円未満の方。
(3)同世帯の被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満の方。
(4)同世帯の被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方。
医療費が高額になったとき[高額療養費]
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えると、高額療養費として払い戻されます。
新規に加入する際に高額療養費支給申請書を送付しているほか、役場健康福祉課と税務課窓口に申請書があります。一度申請すると、自己負担限度額を超えた都度、自動的に指定された口座へ振り込まれます。
| 区分 | 自己負担割合 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院 (世帯単位) |
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 3割 |
252,600+(医療費の総額-842,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 3割 |
167,400+(医療費の総額-558,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 3割 |
80,100+(医療費の総額-267,000円)×1% |
|
| 一般2 | 2割 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう |
57,600円 4回目以降は |
| 一般1 | 1割 | 18,000円(注4) | |
| 低所得者2(注1) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(注2) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
- 注1 同一世帯の全員が住民税非課税の人。
- 注2 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
- 注3 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
- 注4 自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けています。
- 注5 令和7年10月1日以降は18,000円となります。
高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月から)
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
| 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
| 現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
| 現役並み所得者1 | 670,000円 |
| 一般1・2 | 560,000円 |
| 低所得者2 | 310,000円 |
| 低所得者1 | 190,000円 |
保険料の滞納を続けていると・・・・
保険料を滞納した場合、督促状が送付されます。督促状が送付されると督促手数料100円を加えて納めることになります。また、納期限までに納めた人との保険料負担の公平性を保つために、延滞金も納めることになります。
なお、特別な事情もなく保険料を滞納し、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
・短期被保険者証の交付
通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
・被保険者資格証明書の交付
特別な事情もなく一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、一旦全額自己負担となります)
・医療給付の制限
特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの医療給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。
滞納処分
納付する意思がない場合や相談に応じない場合は、法律に基づいて滞納処分が行われ、預貯金、給料、不動産などの財産の差し押さえや公売手続きなどの処分を受けることとなります。
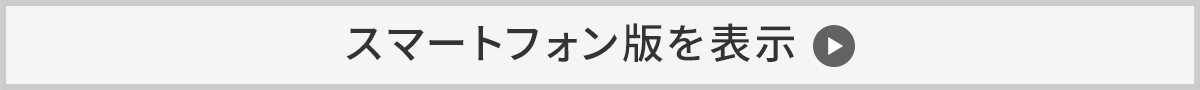







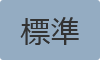




更新日:2024年12月16日